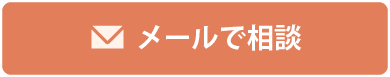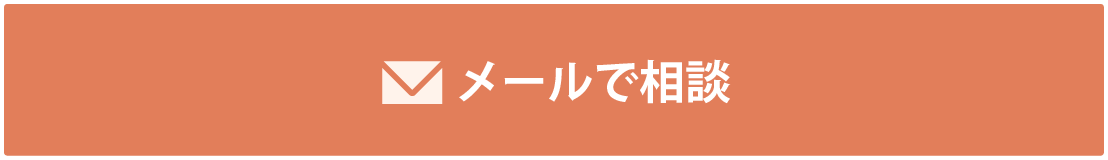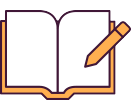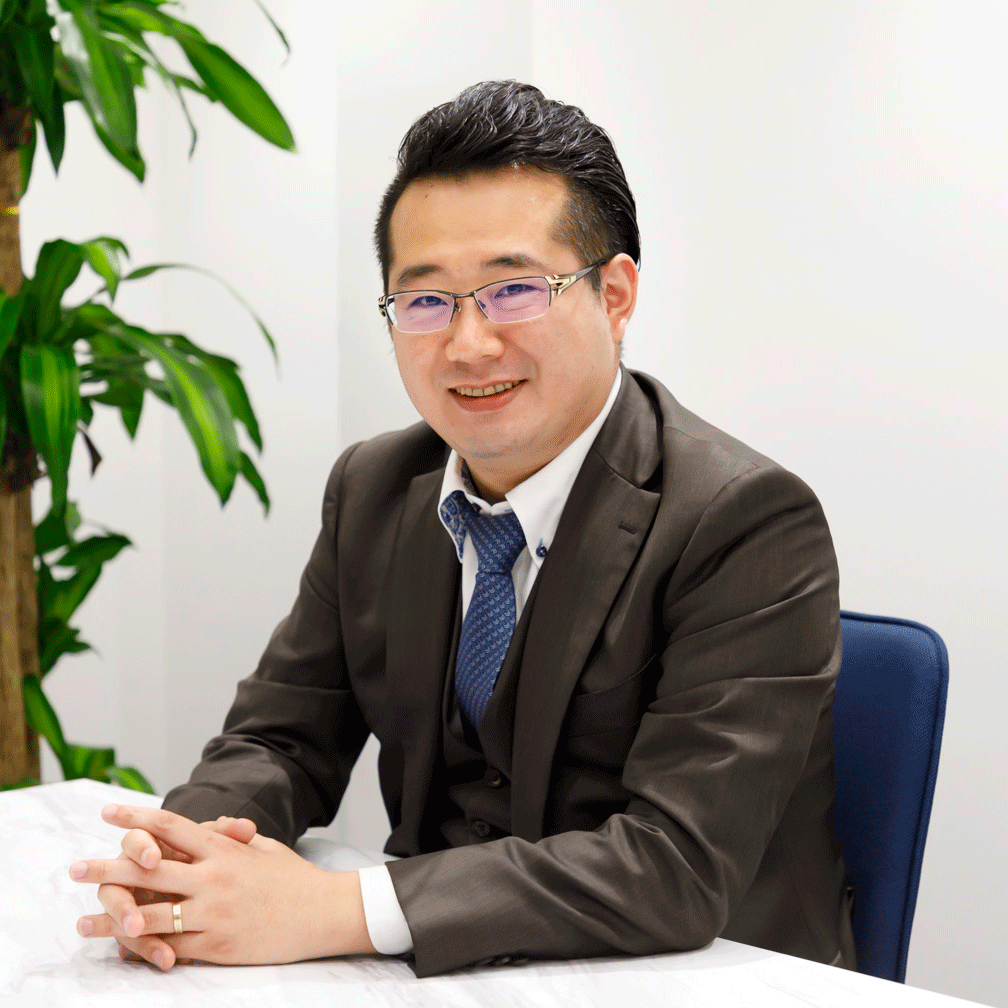借地非訟とは?
種類と手続きの流れ
借地非訟の制度 要点10秒解説
-
地主が譲渡・転貸・増改築などの承諾を拒否した場合、裁判所が代わって許可を出せる制度(非訟裁判)。
-
非訟裁判は譲渡・転貸、増改築、条件変更、競売または公売の譲り受けの許可のみ
-
地主にも「介入権」が認められ、裁判手続への関与が可能。
-
非訟裁判は、地主との協議がどうしても進まない場合の「最後の手段」とされる制度です。
借地権買取対応エリアは1都3県になります。
一部エリア内でもご希望に添えない可能性があります。
目次〔開く〕
借地権相談所では、借地人様や地主様が安心してご相談いただけますよう、相談料はもちろん、事前調査費用や出張費など一切いただいておりません。どうぞお気軽にご相談下さい!
借地非訟とは
借地権の売却(譲渡)の際には、必ず地主の承諾が必要となります。
但し、地主が譲渡承諾を認めないケースも少なくありません。
しかしそれでは、買い手も見つかって、いざ売却(譲渡)というときに借地権者様は大変困ってしまいます。
正当な理由があるにもかかわらず、譲渡承諾を得られない場合には、
「借地非訟(制度)」
を利用することが出来るのです。
借地非訟制度とは、一言でいうと
「承諾をしてくれない地主に対して、裁判で正当事由を明らかにし法の下で承諾を得る」
という制度が借地非訟です。
裁判所は、借地権の譲渡先が地主にとって不利益がないか、譲渡に関して正当な事由があるかなどを調査します。
その結果、裁判所にて認められれば、地主に代わって売買契約の許可を出してくれるのです。
ただし、裁判に持ち込む、ということですから地主との紛争状態なり、結果的には関係が悪化する事にもつながります。
まさに、借地権者様にとって借地非訟は「最後の手段」といえる制度でしょう。
借地非訟の種類
借地非訟の申し立てには下記の種類があります。
土地賃借権の譲渡または転貸の申立て
賃借人(借地人)は賃貸人(地主)の承諾を得なければ借地権の譲渡や転貸を行うことができません。
もし、地主が借地権の譲渡や転貸を承諾しない場合、借地借家法では賃借権の譲渡や転貸に関し賃貸人に不利となる恐れがないにもかかわらず承諾しない場合には、借地権者の申立てによって裁判所が地主に代わる許可を与えることができると記載されています。
借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、賃借権の譲渡若しくは転貸を条件とする借地条件の変更を命じ、又はその許可を財産上の給付に係らしめることができる。
参照:e-gov借地借家法第十九条 【土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可】
借地条件変更申立て
借地上の建物は、その種類、構造、規模、用途などが土地賃貸借契約書上で制限されていることが多くあります。
例えば、木造3階建ての建物が老朽化しているため、鉄筋コンクリートなどの5階建てのビルに建て替えたい場合、土地の所有者(地主)との間で非堅固建物から堅固建物への借地条件の変更承諾が必要となります。
その際に、地主との間で条件変更の合意が得られないことがあります。
このような場合には借地権者は借地条件変更の申立てを行い、裁判所は借地条件の変更をするができるとされています。
建て替えに伴う条件変更は、条件変更の承諾及び建て替えの承諾も必要になります。
建物の種類、構造、規模又は用途を制限する旨の借地条件がある場合において、法令による土地利用の規制の変更、付近の土地の利用状況の変化その他の事情の変更により現に借地権を設定するにおいてはその借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当であるにもかかわらず、借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、当事者の申立てにより、その借地条件を変更することができる。
参照:e-gov 借地借家法第十七条 借地条件の変更及び増改築の許可
増改築許可申立て
借地契約では、建物の建替えや増築などを行う際、土地所有者の承諾が必要です。
しかし、承諾が得られない場合、借地権者は裁判所に増改築許可の申立てを行い、裁判所が許可すれば、その許可が土地所有者の承諾に代わります。
建て替えに伴う条件変更は、条件変更の承諾及び建て替えの承諾も必要になります。
増改築を制限する旨の借地条件がある場合において、土地の通常の利用上相当とすべき増改築につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、その増改築についての借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
参照:e-gov 借地借家法第十七条2項 借地条件の変更及び増改築の許可
競売または公売に伴う土地賃借権譲受許可の申立て
借地権付き建物を競・公売で購入した人は、土地賃借権の譲渡に対して土地の所有者(地主)の譲渡に係る承諾を得る必要があります。
その際に、土地の所有者が譲渡を認めないときに、購入者は裁判所に競売または公売に伴う土地賃借権譲受許可の申立てを行い、土地所有者に代わる許可を受けることができます。
この申立ては、購入後2か月以内に申立てを行わなければなりません。
第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売又は公売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、借地条件を変更し、又は財産上の給付を命ずることができる。
第一項の申立ては、建物の代金を支払った後二月以内に限り、することができる。
参照:e-gov 借地借家法第二十条、二十条3項 建物競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可
更新後の建物再築許可申立て(平成4年8月以降に設定された借地権)
借地契約更新後に、特別な事情で建物を建てる際、土地所有者の承諾が必要になります。
しかし、その承諾が得られない場合、借地権者は裁判所に更新後の建物再築許可の土地所有者に代わる許可を受けることができます。
再築する建物が契約条件と異なる場合は、再築許可申立てとともに、借地条件変更の申立ても行う必要があります。
契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、延長すべき借地権の期間として第七条第一項の規定による期間と異なる期間を定め、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。
参照:e-gov 借地借家法第十八条 建物競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可
借地権買取対応エリアは1都3県になります。
一部エリア内でもご希望に添えない可能性があります。
介入権の行使
特定の条件下で裁判所によって設けられる特別な権利であり、この権利を行使することで、借地権設定者は自らの権益を守る行動をとることが可能になります。
介入権とは
借地権者が土地賃借権の譲渡または転貸の申立て、競落者が競売または公売に伴う土地賃借権譲受許可の申立てを行った際に、優先的に土地所有者(地主)が借地権付き建物を買取ることができる権利です。
介入権は借地権設定者が行使できる権利
借地権設定者が、裁判所が承認する一定期間内に、自己の借地権に影響を与える可能性のある訴訟等に対して介入し、その権利を主張できる法的な権利です。
この権利の主な目的は、借地権設定者が自己の権益を守り、土地の有効活用を図ることにあります。
介入権を行使できる期間
借地権者もしくは競落者から譲渡許可などの申請が行われた際には、裁判所は借地権設立者(地主)に対して介入する権利を行使するための期限を設定します。
その期限内に借地権設立者(地主)がその権利を用いると、裁判所は土地鑑定委員会が算出した価格(借地権の取得代金)に基づいて、借地権設立者(地主)に対して介入権を行使するかの判断をゆだねます。
借地権設立者(地主)は介入権を必ず行使しなければならないという事はなく、介入権を行使しなければ譲渡許可の裁判が継続する形になります。
なぜ、承諾を嫌がるのか
地主はなぜ、なかなか承諾をしてくれないのでしょうか?
そこには地主の考えとして、
というような理由が多いといわれています。
両者にとってメリット、デメリットが混在するため、紛争になりやすいことが多いのです。
借地非訟の申立て費用の目安
申立てにかかる裁判所に支払う手数料は下記が目安となります。その他、弁護士費用など別途費用が掛かります。
| 目的物の価格 基礎となる額 |
手数料 | 目的物の価格 基礎となる額 |
手数料 |
|---|---|---|---|
| 500万円 | 12,000円 | 5500万円 | 74,000円 |
| 1000万円 | 20,000円 | 6000万円 | 80,000円 |
| 1500万円 | 26,000円 | 6500万円 | 86,000円 |
| 2000万円 | 32,000円 | 7000万円 | 92,000円 |
| 2500万円 | 38,000円 | 7500万円 | 98,000円 |
| 3000万円 | 44,000円 | 8000万円 | 104,000円 |
| 3500万円 | 50,000円 | 8500万円 | 110,000円 |
| 4000万円 | 56,000円 | 9000万円 | 116,000円 |
| 4500万円 | 62,000円 | 9500万円 | 122,000円 |
| 5000万円 | 68,000円 | 1億円 | 128,000円 |
| 目的物の価格 基礎となる額 |
手数料 |
|---|---|
| 500万円 | 12,000円 |
| 1000万円 | 20,000円 |
| 1500万円 | 26,000円 |
| 2000万円 | 32,000円 |
| 2500万円 | 38,000円 |
| 3000万円 | 44,000円 |
| 3500万円 | 50,000円 |
| 4000万円 | 56,000円 |
| 4500万円 | 62,000円 |
| 5000万円 | 68,000円 |
| 5500万円 | 74,000円 |
| 6000万円 | 80,000円 |
| 6500万円 | 86,000円 |
| 7000万円 | 92,000円 |
| 7500万円 | 98,000円 |
| 8000万円 | 104,000円 |
| 8500万円 | 110,000円 |
| 9000万円 | 116,000円 |
| 9500万円 | 122,000円 |
| 1億円 | 128,000円 |
※あくまで目安となります。申立て時に裁判所にてご確認ください。
参照:裁判所 第3 費用
借地権買取対応エリアは1都3県になります。
一部エリア内でもご希望に添えない可能性があります。
借地非訟裁判の流れ
① 申し立て
借地権が存する所在地を管轄する裁判所に必要書類を提出して譲渡などの許可申し立てを行います。
② 審問
裁判所は必要書類の確認を行い審問期日を設けます。おおよそ1ヶ月程度で期日は開かれます。この審問は数回行われます。
③ 鑑定委員会の意見聴聞
借地権に関する非訟事件で裁判所が正しい判断を下すためには、専門的な知識が必要です。
例えば、建て替えや名義変更の際に借地権者に支払うべき譲渡承諾料や、借地権設定者が介入権を行使した場合に支払うべき建物や土地使用権の妥当な価格を決める際には、不動産の価値を正確に把握することが欠かせません。
このような複雑な問題を解決するために、裁判所は専門家で構成される鑑定委員会を設けています。この委員会には、不動産や法律に詳しい弁護士、不動産鑑定士、建築士などの有識者が3人以上含まれており、彼らが裁判所に対して公平かつ客観的な意見書を提供します。
この制度により、借地権に関わる問題について裁判所は、専門的な視点と民間の良識を反映した適正な判断を行うことができるようになるのです。
④ 和解勧告・決定
裁判所は鑑定委員会の意見を聞いた後、当事者に和解による解決を勧めます。借地権は裁判後も借地契約が継続する場合が多くあり円満に解決が望ましいからです。
和解による解決ができない場合、裁判所は裁判に基づく決定を行います。
この決定により裁判は終了します。裁判所は決定書を作成し当事者に正本を送達します。
参照:裁判所 借地非訟事件の流れ
借地非訟のメリットデメリット
借地非訟裁判にもメリットデメリットが存在します。
借地非訟のメリット
借地権に関するトラブルを公平に解決する手段として、借地非訟事件が有効です。
この手続きでは裁判所が事実を客観的に調査し、当事者の主張に左右されることなく判断を下すため、公正な解決を図ることができます。
また、調停とは違い、裁判所が最終的な決定を下すので、紛争を強制的に解決することも可能です。
さらに、裁判所の決定前に当事者同士で交渉して解決することもできるため、柔軟な対応が望めます。早期に合意に至れば、手続きを短縮し、コストを抑えることもできます。
借地非訟のデメリット
借地非訟は、公平な判断を下さなければならず、多くの審問期日が必要とされ最終的な判断まで長期間要してしまう事です。
また、長期化すれば裁判費用などの出費が多くなり経済的負担が大きくなります。
借地権相談所による借地非訟
借地非訟を行うには正当事由と、地主に不利益の無いことを証明しなくては、裁判所は代諾許可を行ってくれません。
裁判となると時間もかかり、地主との紛争に借地権者様が直接関わることになり、関係も非常に悪化してしまいます。
また、借地非訟を弁護士などに依頼をしても、費用がかさんでしまい売却してもその分が経費としてマイナスとなってしまいます。
当社に借地権の売却を依頼された借地権者様でも、地主から承諾を得られない場合もございます。
そこで当社で借地非訟に関する事前相談からアドバイザー業務まで借地権者様をバックアップ出来る体制が整っております。
売却したいのに売却できない借地権者様は数多くいらっしゃいます。
地主が譲渡承諾してくれないことをあきらめずに、まずは当社にご相談ください。
借地非訟はあくまでも最終的な手段に近く、借地非訟を起こせばすべてが解決するということではありません。
借地非訟等を含めて、様々な角度から最善の解決方法をご提案させていただきます。
借地権買取対応エリアは1都3県になります。
一部エリア内でもご希望に添えない可能性があります。